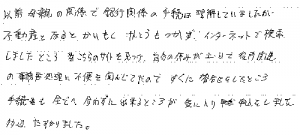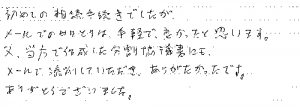【Question】
個人的に金銭を貸し付けていた、取引先の社長が亡くなりました。
そこでご遺族に借金を返済するよう求めたのですが、ご遺族の話では、財産よりも負債のほうが多かったので相続人全員が相続放棄したとのことで、家庭裁判所が発行した証明書も確かに見せてもらいました。
しかし、生前の彼は派手好きで、スーツや靴などは高級なものを身につけていましたし、輸入品のガラス器も大切にしていました。また、絵画やヴィンテージワインを集める趣味もありました。これらのほとんどは、相続放棄後に一部の遺族の方が形見分けと称して持ち出したようです。
確かに彼は借金も多かったようですが、価値のありそうな遺品の大半を持ち出した遺族が相続放棄できて、債権者である私は何も請求できないというのは釈然としません。
【Answer】
故人を偲ぶ程度の遺品を相続人間で分け合う『形見分け』については、民法921条1号の「相続財産の処分」にあたらず、それが相続放棄の後になされた場合でも同3号の「相続財産の隠匿」等にあたらないとされています。通常の形見分けによって単純承認したものとみなされることはありません。
しかし、たとえば遺品に新品同様の衣服・靴等が多数含まれている場合や高価な宝石などは、一定の財産的価値を有している以上、これを勝手に持ち出す行為は通常の形見分けの範囲を超えています。そもそも相続放棄した遺族には、その放棄によって相続人となる者のために相続財産を管理する義務があるのです(民法940条)。
相続放棄した後であっても、相続財産を持ち出し、被相続人の債権者に損害を与えるような背信的行為をした相続人に対して、相続放棄によるメリットを与えるべきではありません。
そこで、利害関係人に損害を与えるおそれがあることを認識しながら相続財産を隠した場合には、民法921条3号の「相続財産の全部または一部または隠匿」にあたり、制裁的に相続を単純承認したものとみなされる可能性があります。
なお、相続人が、相続放棄の申述を受理された後、故人のスーツ・毛皮コート・靴・絨毯等一定の財産的価値を有する遺品のほとんどすべてを自宅に持ち帰った行為が、いわゆる形見分けを超えるものであって「相続財産の隠匿」にあたるとした地裁判例があります(東京地判平成12年3月21日家月53巻9号45頁)。
【Reference】
法定単純承認 ~相続を承認したものとみなされてしまうケース~
自分から「相続を承認します」という意思を明らかにしなくても、他人から見たら相続を承認したような事実があれば、相続人は単純承認したものとみなされます。これを法定単純承認といい、次のような場合がこれにあてはまります(民法921条)。
(1)相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき
・「処分」には、相続財産の事実上の処分(例:取り壊し)と、法律上の処分(例:譲渡)の両方を含みます。 ・単に建物の修理のような遺産の値打ちを維持するだけの行為や、短期の賃貸借契約(たとえば土地なら5年、建物なら2年以内の期間の賃貸借契約)は除きます。
(2)相続人が相続放棄や限定承認の手続きを取らず、3ヶ月の熟慮期間(Q079)を過ぎたとき
(3)たとえ相続放棄や限定承認をした後でも、相続財産の全部または一部を、(a)隠したり、(b)債権者に隠れてこっそり消費したり、(c)隠すつもりで限定承認をしたときに作成する財産目録に載せなかったりしたとき
このようなケースにあてはまって法定単純承認が成立すれば、もはやその後に相続放棄することはできません。 たとえ熟慮期間中であったとしても、法定単純承認を生じさせた行為を撤回することは原則としてできず(民法919条1項)、相続人は無限に被相続人の権利義務を承継することになります(民法920条)。
厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂
厂厂厂厂
厂厂厂 ©司法書士法人ひびき@埼玉八潮三郷
厂厂
厂 無断転載禁止