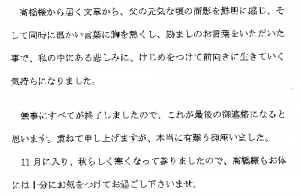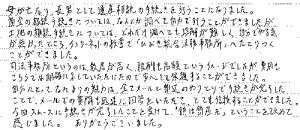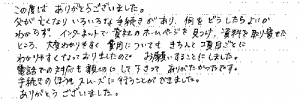【Question】
先月、夫が亡くなりました。相続人は妻である私・長男・長女の3人です。
夫の遺産は自宅の建物だけで、土地は借地です。
この家に済んでいるのは私一人だけですが、私は今までどおりこの家に住むことはできますか。
【Answer】
まず、借地が『賃貸借契約』の場合(相応の地代を払っている場合)には、今までどおり住み続けることができます。
地主さんの承諾は必要ありません。
注意点としては、借地が賃貸借契約の場合には借地権にも財産的価値があり、その価値が高いこともありますので、遺産分割で問題になることがあるという点です。
遺産分割が終わったら、建物について相続登記(名義変更)をします。賃借権も登記されている場合には登記が必要です。
もしも、借地が『使用貸借契約』の場合(地代を払っていない場合)には、地主さんから建物の撤去・土地の明け渡しを要求されるかもしれません。
使用貸借契約では地主さんから明け渡しを請求されたら住み続けることはできませんが、交渉の余地はあるかもしれません。
なお、賃貸借契約でも、地代が非常に低く固定資産税の額程度の場合には、実質的には使用貸借契約と言えますので、明け渡しに応じなければならないこともあります。
【Reference】
借地の借主が亡くなった場合には、地主さんに対する地代の有無によって結論がまったく異なります。
賃貸借契約の場合
相続人は、被相続人の一身に専属する権利を除き、被相続人の権利義務いっさいをそのまま承継します。
借地権(賃借権・地上権)も被相続人の財産であり相続の対象となりますので、何ら手続きをしなくても相続人が承継します。
借地の使用目的が居住用でも事業用でも同じです。
相続人は被相続人の権利義務いっさいをそのまま承継しますので、借地権を第三者に譲渡するわけではありませんから、地主さんの承諾は必要ありません。
遺産分割が終わるまでの間は、借地権は相続人の間で共有(準共有)することになり、相続人全員が相続分に応じて借地を使用する権利がありますので、ご相談者は自宅に住み続けることが可能です。
もちろん遺産分割が成立すれば、借地権を相続した相続人が単独で借地を使用することができます。
よくある話として、借地の相続人に対し地主さんから『名義変更料』『更新料』などの名目で金銭を請求されることがあります。
これは法律的にはまったく根拠がありませんので、請求に応じる必要はありません。応じなくても違法ではありません。
もちろん、地代はきちんと払わなければ地主さんから契約を解除され、土地を明け渡さなければなくなってしまいます。
遺産分割協議が成立するまでは相続人各自が賃料全額を支払う義務があります。
なお、地代を払っているといっても、その地代が非常に低額で固定資産税の額程度であれば、それは後で解説する『使用貸借契約』と考えられ、結論は正反対になります。
使用貸借による借主は借用物の通常の必要費を負担するものとされており(民法595条1項)、その土地の固定資産税は借主が負担するのが通常であるからです。 これは名目ではなく実質で判断しますので、地代として払っているけれどもその額が固定資産税の額程度ならばそれは賃貸借ではなく使用貸借として扱われます。
借地権の遺産分割
注意点としては、借地上の建物が古くほとんど価値がない場合でも、借地権は意外と財産的価値が高いという点です。
借地権の価額は、土地の更地価額の50~70%で評価されるため、遺産分割の際に問題になることがあるのです。
ご相談者のように借地上の建物を利用したい相続人がいる場合で、相続人全員による遺産分割がすんなりとまとまらなければ、次のような方法で遺産分割協議を成立させていくことが考えられます。
1)建物と借地権の現物を取得する相続人が、代わりに法定相続分を超える部分の価額に相当する金銭を他の相続人に支払う(代償分割)
2)地主さんや第三者に建物と借地権を買い取ってもらって、その代金を相続人で分ける(換価分割)
使用貸借契約の場合
土地を無償で借りているような場合を『使用貸借契約』といいます。
使用貸借契約は、貸主と借主の特別な関係によって成立する契約ですので、借主の一身に専属ずる権利と考えられており、相続の対象となりません。借主の死亡によって当然に契約が終了してしまいます。
そのため、地主さんから明け渡しを請求された場合には、それに応じなければならなくなります。 しかも、地主さんは借主に対して建物を解体した上での土地明け渡しを請求できますので、相続人が解体費用を負担しなければならなくなります。
そのため、まずは地主さんに今までどおり使用貸借させてもらえるよう交渉し、それが受け入れられなければ賃貸借契約に切り替えてもらうか、または転居する代わりに建物解体費用を負担してもらうかを交渉していくことになるでしょう。
厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂
厂厂厂厂
厂厂厂 ©司法書士法人ひびき@埼玉八潮三郷
厂厂 お問い合わせはこちら
厂 無断転載禁止